11月25日実技講習会に行ってきました。
持ち物は、ハンドブックと問題集。。ですが、ハンドブックは学科実技共に高価で買えなかったので
当日は忘れたことに。あまり困りませんでした。講師の方達の指導に耳を傾ける時間と実践する時間がほとんどです。
4人1テーブルで先生は2テーブルに1人ついていました。
ちなみに、のこぎりも、木工バイスもさしがねもミニサイズでした。
講習会での実習は、以下のとおり。
- 木材組み手(三枚継ぎ手、相欠き継ぎ2パターン)墨付けとのみ、鋸の使い方
- ダボ継ぎ(ダボ用ピンを用いる)
- ジグソーでのくり貫き
- ゴムとゴムの接着
- アクリルの接着
- タイルの合板への接着と目地の充てん
- 中空壁用アンカーを使ったフックの取り付け
- ドアの錠取り外し、取り付け
- 湿潤壁紙を張る
と、せわしなくどんどん講習が進められ・・・
組み手はやっぱり時間がかかります。
何がっ?て、組み手によって墨つけのポイントも違ってくるし、小口にノミを使う時にはたいへん時間が取られます。木端にノミを使う場合に比べて何倍も崩しにくいの!!
木材の墨付けから組むまでを何度も練習して時短を計らねば!!
接着は、1回やると覚えるし、時間も足りなくはならないと思うので、講習だけでOKですな♪
アンカー類は失敗している人もいました。
安価だし、試験の少し前に家でもう一度やっておこう♪
モリーアンカーは、まず玄翁でねじごと打ち込まないといけないのに、いきなりネジを廻し、アレ????
となっていた私でした。最初の打ち込みは、玄翁だっけ?手だっけ?ネジだっけ?とならないように頭を整理しておかないと・・。
壁紙も講習だけでいけそう。
錠の組み立ても意外と大丈夫だったので、これも講習だけでOK。
他、講習ではやらない以下の道具が展示してあり、それらにさわれたり、先生方に質問できたりとこの辺りがたいへんよかったなぁと思います。お昼休みと講習終了後に触ってみました。
お昼休みは長くはなかったけれど、うどん屋でさっと食事を取った後時間があったので、いろいろ触ることができました。
コーナーの台に置いてあり、触ってみた道具たちはこちら↓
- 水道蛇口 レバーハンドルも
- 蛇口の根元に巻くシール・・・・巻いてみました。調整パッキンもおいてありました。
- タッカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・玉の入れ替え方を確認できました。
- ボールタップ(トイレ水栓)・・・・ネジをはずして、弁体のパッキンをつけ外ししました。
- Sトラップ・・・・・・・・・・・・・・・・・つなぎ目をはずし、平パッキン、スリップパッキン、パイプパッキンのセッティングの確認と、パイプをつなぐ練習をしました。
- 隠しクギ・・・・・・・・・・・・・・・・・実際に打ち込んで、頭を飛ばしました。
- オービタルサンダー・・・・・・・サンドペーパーの着けはずしを確認してみました。
実技採点ポイント
- 墨付け 差し金が正しくつかえているか。
- のこ、ウマが使えているか。
- のこは、タテびき、ヨコ引きの使い分けができているか。
- 完成させる。(精度は求められない。)
継ぎ手の完成ポイントは、上記に加え、片方を持っても取れないことだそうです。
他、安全に道具が使用できるかが重要ポイント。
実技講習で注意されたこと
- 玄のうの持ち位置が短い。
- クランプ使用忘れ ➡ 10点減点 (◞‸◟)安全に作業できない人とみなされる。もう30点減点だよ!って怒られちゃいました。
ポイントのまとめ
■差し金・墨付けのポイント
実寸の目盛りの面を使用する。裏面を使用すると1.4倍の寸法になってしまうので注意。
差し金目盛り値 10 20 30 が赤文字 の面を使う。
- 木端にも墨付けを。
- 墨付けは、濃く。
- 現物を当てて墨付け。
■相欠き継ぎ手(クロスtype)
相欠き継ぎ手は、容易にノミで欠くことができる、表からと裏からとでノミで攻める。
■相欠き継ぎ手(端っこ渡すtype)
墨付けは、どのサイズをどこに移し取るかがポイント。
この墨付けも慣れておくこと。
■三枚継ぎ手
ポイント➡きついめに作る
墨付け・・もらったプリントの墨付け手順を覚える。
2等分したきれいほうの小口を使う。
- 男木と女木を付き合わせ、
- 板巾3等分の墨付けをする
- 食い込みは、板厚であるので、片方を立てて、板厚を写す。
男木をタテ引きとヨコ引きを使い、完成させて
女木にあてて女木の墨線のどの辺りを切るか見当をつける。
(女木はのみを使うので、時間がかかる。木口側の欠きになるので、ほんとうに硬くて削るのに手こずる)
■コードレスドリル
切り替え・・・左からボタンを押すと、右へボタンが移動する
=この状態が通常の回転方向。
真ん中で止めると、ロック
この状態でビットを脱着させると、安全に作業を遂行していると見なされる。
■ダボ接合のポイント
- ダボ穴開けのドリルに巻くビニールテープは、深いめに設定する。
- ダボ自体きついめに入るので、ダボ穴が深すぎてもバレない。
- マーカーを印しておくと、裏表を間違えないで済む。
■ゴムとゴムの接着 =合成ゴム系接着剤
ヤスリは必要なエリアだけ
両方に薄く付ける。
混ぜてはいけない。ヘラは、一方向のみ一回撫で。
アクリルの接着が終わるまで放っておく。
■アクリル接着=
- アクリルの墨付け
- 3分の1ラインを2本引く。
- 1方は、立てる方のセンターラインにするので、誤って切らないこと。
- 紙を剥がさず、アクリルを切る。
- 定規は厚みのある方を使用。
- ギイギイ切り込みを入れたら、切込みをテーブルの端に合わせて体重をかけ、割る。
- 3分の1と3分の2に分かれる。
- 3分の1の方だけ紙を剥がす。
- 机上に置いたやすりで、断面を磨く。
- 3分の2を机に置く。
- スポイドに接着材を少量吸わせ、3分の1の方をセンター上に少し傾けて立て
- スポイドを隙間に注入。
- 速乾なので、すぐに裏の紙が剥がせる。
- スポイトにあまった分は、すぐに瓶へ。
アクリルが終わったら、丁度オープンタイムが消化したころ。ゴムの接着だ。ハンマーで叩く。
■タイルの接着・・・酢ビ溶液系接着剤
ツルツル面に切り込みを入れる。(嫌な音じゃ。)
切る時は、カッターの持ち手は、タイル側が平らな面になる様に持つ。
グー持ちでもよいので、ガリガリ言わすくらいに力を入れる。
前後の向きを変えて、奥だった部分を切り直す。
切り目が入ったら、机の端の外側に切り目ラインを持っていき、
カッター反対側の挟む部分でタイルを挟み、親指の付け根を当てるように親指の付け根のふくらみを添える。(挟む工具と手は、机の外側)
接着剤 まんまタイルは、こんもり 9こ 点付け。
1/2タイルは、こんもり 6こ点 付け。
目地巾・・指定なき場合は、適切な目地巾は、3mm
目地ならしは、細い方を用い、膨らんでる方を天に向ける。
■中空カベ用アンカー
玄のうで入れる・・・・
■トグラー (折りたたんでから玄翁で打ち込み、付属の細棒を入れると壁の向こうで羽が広がる)→フックの取り付け
■モリーアンカー(ネジごと) 打ち込み後、付属のレンチを噛まし、ネジを締める。レンチをはず し、 ネジを一旦外す→フックの取付。(レンチを噛ますのはモノマックスの付け根が空回りするのを防ぐため)
■石膏クギ(各穴に、クギを打ち込み、最後にキャップ)
■ モノマックス 打ち込み後、ドライバーで
ドライバーで入れる・・
■カベタップ
カベタップと石膏クギ以外は、ドリルで穴あけが必要。
■円筒錠
軽く穴に針状の金物(真っ直ぐな側)を入れながら、ノブ根元を引っ張りながら取る
→ポンッと取れる。
室外側から組み立てる。
はめるときは、丸座裏金の裏にUPと書いてある方を上に取り付ける。
ノブの取り付けは、押し型を溝にあわせる。
■インテグラル錠
引っ掛けタイプの金物を穴に引っ掛けて廻す。
室外側から組み立てる。
ノブを取り付けるときは、まず、半月盤を合わせながら他の部分を合わせながらはめ込む。
デッドボルトを出した状態で、サムターンの向きを横向きに合わせる。
■壁紙貼り
壁紙・・・・重なりの中心にカッターを入れる。
下のほうが切りにくいが頑張る。
そして、
カッターは一度も壁紙からはなしてはいけない。
カッターをさしたまま、金べらをずれしていく。
水たっぷり。置くようにつけていく。
右側から貼る(右は右端に合わせ、左は左端に合わせる)
1.水つける。
2.ひと呼吸置く
3.先に水を付けた紙から貼る。
4..なで刷毛で空気を逃がしながら押さえていく。
5.竹ベラで上下のラインを決め込む。
6.金属ベラ・・上端は、金属ベラの上をカッターで切る。下端は、金属バラの下をカッターで切る。
逆にすると、それぞれ短くなり、寸足らずになるから。
7.ローラーでコロコロする。
8.重なり中心部に、カッターを入れる。この時、
合板を切るくらい深く切ること。
■ガンタッカー
ステンレスのヘッドを左手で押さえる。
ステープル(ホチキスの芯みたいなもの)を入れるにあたり、上下の向きをまちがえないこと。
Uの字にセッティングする。
これも展示コーナーのもの
右から2番目:ダボ用ドリルの先は、爪みたいになっており、1巻き目が円を描けるような作りになっている。その隣の木工用は、先端がネジになっている。





















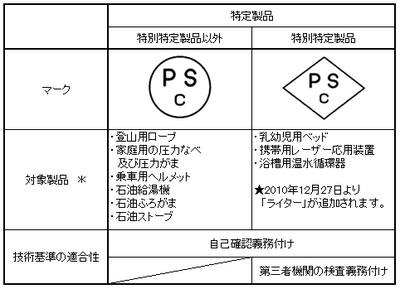

 ←
←